
1968年は政治の季節と言われる。フランスで五月革命、米国では激しいベトナム反戦運動が発生。チェコスロヴァキアでは「人間の顔をした社会主義」の試みが始まったが、ワルシャワ条約機構の戦車によって潰された。
日本では三派全学連と各県・各地区の反戦青年委員会が各地でダイナミックな運動を展開していた。東大安田講堂占拠が起きたのもこの頃である。
各国の反体制運動は各国の事情で様々だが、アメリカでは大学内の紛争が主流、フランスの大学紛争は労働組合と連帯してゼネストへと進んだ。西ドイツでは労働組合から支持されず主に学生の改革運動となった。日本では中核派、解放派の反戦部隊が激突し、反戦青年委員会も両党派の軍団化した部隊による内ゲバ的激突で急速に支持を失った。
反戦青年委員会とは、
主にベトナム戦争反対を掲げた日本の青年労働者による大衆団体。
正式名称は「ベトナム戦争反対・日韓批准阻止のための反戦青年委員会」※ベトナム戦争:1964年のトンキン湾事件以後アメリカ合衆国が大規模に介入し,1973年のパリ和平協定を経て 1975年のベトナム民主共和国(北ベトナム)と南ベトナム解放民族戦線(解放戦線)の勝利によって終わった。
※日韓条約:1965年6月に、日本(佐藤栄作政権)と韓国(朴正煕政権)との間で調印された条約。同条約は15年にわたる交渉の末に調印されたが、調印と批准には両国で反対運動が起きた。両国間交渉の問題点は賠償金であったが、交渉の末、総額8億ドル(無償3億ドル、政府借款2億ドル、民間借款3億ドル)の援助資金と引き換えに、韓国側は請求権を放棄した。
全国反戦の再建
1966年に再建したばかりの三派全学連は、ブンド、解放派、中核派の党派軍団に分かれて1.羽田闘争、2.佐世保闘争、3.王子野戦闘争、4.三里塚闘争などの闘争を展開した。
これら闘争に革マル派全学連、自治会共闘が独自隊列で加わる状況となった結果、各党派間の対立は激しさを増し、その影響は各県・各地区の反戦青年委員会にも及んだ。前述した東京反戦の機能麻痺は、その典型である。
しかし1968年当時、各県レベルの反戦青年委員会で東京反戦の機能マヒは例外であり、その他の県反戦では中核派、革マル派、解放派などが社青同(日本社会主義青年同盟とは、青年を構成員とする青年政治同盟である。以前は日本社会党と支持協力関係を持っていた。)各地本のイニシアティブを受け入れ、呉越同舟の関係が継続していた。各県反戦はその大衆性を生かし、各地でダイナミックな運動を展開していた。
1.羽田闘争:1967年(昭和42年)10月8日と11月12日に、佐藤栄作総理の外国訪問阻止を図った新左翼と羽田空港を防衛する機動隊が衝突した事件である。新左翼側はこの事件を羽田闘争と呼び、特に10月8日の第一次羽田闘争を10.8(ジッパチ)と称して特別視している。この事件で確立した、ヘルメット(ゲバヘル)に角材(ゲバルト棒)という武装闘争の装いや党派ごとに運動に参加するという高度世様式が確立された
2.佐世保闘争:1968年1月にアメリカ海軍の原子力空母エンタープライズの寄港に対して発生した革新政党・団体・住民を中心とした反対運動
3.王子野戦闘争:敗戦後、米軍に接収されたこの地域。1958年に北側の一部を返還した後、1961年よりキャンプ王子と呼称。1966年に部隊ハワイ移転のため閉鎖されたが返還されず、1968年にベトナム戦争開戦のため米陸軍王子病院(王子野戦病院)が開設される。1969年12月病院閉鎖。返還後は北区中央公園・十条駐屯地・東京成徳短期大学・公務員宿舎となった。
4.三里塚闘争:千葉県成田市三里塚農民を中心とする新空港建設反対闘争。1966年(昭和41)7月4日の閣議で新国際空港を三里塚に建設することが決定するが、これに先だつ6月28日、地元農民は三里塚新国際空港反対同盟を結成、反対運動を開始した68年初頭から三派系全学連の支援が本格化し、警察機動隊との衝突が続いた。
1968年は学生と青年労働者の自発的エネルギーが、一挙に噴出した年で、1.ベトナムにおけるテト攻勢、2.フランスの5月革命、3.神田カルチェ・ラタン闘争、4.アメリカでのスチューデントパワーの爆発、5.チェコスロバキア(プラハの春)などの事件が起きた。
これらの出来事は「世界を変えることができるかも知れない」と日本の青年労働者、学生に多大なインパクトをもたらした。また、同時期に闘われた日大、東大の全共闘運動には、学内的要求に根ざした固有の課題があったが、世界的な情勢への共感が存在していたと思われる。
1.ベトナムにおけるテト攻勢:1968年1月30日夜から展開された北ベトナム人民軍(NVA)及び南ベトナム解放民族戦線(NLF)による、南ベトナムに対する大攻勢。「テト」とは「節」という漢字のベトナム語読みで、ベトナムの旧正月を指す。
2.フランスの5月革命:1968年5月10日に勃発した、フランスのパリで行われたゼネスト。5月2日から3日にかけて、カルチェラタン含むパリ中心部で大規模な学生デモがおこなわれた。
3.神田カルチェ・ラタン闘争:1968年6月21日に社学同(社会主義学生同盟。共産主義者同盟(ブント)の学生組織)が東京神田駿河台の学生街で起こした解放区闘争。駿河台の通り2か所にバリケードを築いたが、たちまち機動隊に突破された。(カルチェ・ラタンとはフランス・パリの地区名で学校が集中しており、1968年にフランス学生のデモ五月革命の舞台となる。)
4.アメリカでのスチューデントパワーの爆発:アメリカでは、「いちご白書」1970で有名なコロンビア大学闘争1968や、非暴力学生調整委員会、ウエザーマン、ブラックパンサーにいたる学生運動の高揚があった。
5.チェコスロバキア、プラハの春:1968年に起こったチェコスロバキアの変革運動。8月20日夜11時頃、ソ連率いるワルシャワ条約機構軍が国境を突破し侵攻し、チェコスロバキア全土を占領下に置いた。
ところが全国反戦は、68年3月から機能麻痺=凍結状況が続き、このような新たな情勢対応する全国展開ができない事態が続いていた。そうした中で、「社会党・総評が動かないのならば、各県反戦がまとまって全国反戦を再建すればいい」と考えた宮城県反戦は、69年初頭に上京して全国各県反戦青年委員会連絡会議(全国反戦)の結成を呼びかけた。このオルグは、宮城、埼玉、神奈川、石川、大阪、徳島、福岡、長崎など11県反戦呼びかけの4・20全国集会(沖縄闘争)へと結実したのである。
この時に、全国反戦の世話人に選出されたのが埼玉県反戦からで、新左翼諸党派にとっても社青同反戦派の存在が総評・社会党との関係で重要だったからにほかならない。
こうして全国反戦は、1969年11月の佐藤訪米阻止闘争を頂点とするベトナム反戦闘争、沖縄闘争、三里塚闘争などを全国全共闘、べ平連と並ぶ全国運動のセンターとして、71年6月まで闘い抜いた。
社会党:
社青同:
総評:
佐藤訪米阻止闘争:1969年11月16日~17日に行われた新左翼による闘争・事件。近代日本史上最大の2500人超の逮捕者を出し、1967年から続いた学生運動・新左翼運動の高揚に一つの終止符を打った。
全国反戦の内部対立
しかし全国反戦の再建以降、顕著になったのは新左翼諸党派の内ゲバを含む対立の激化であり、反戦青年委員会の党派軍団化である。
結成スローガンとして自立・創意・統一を掲げた反戦青年委員会運動は、労働疎外と労働組合の官僚化が進む青年労働者の日常から、そのみずみずしい感性を解き放つ場であった。彼らのエネルギーは街頭闘争での戦闘的なデモンストレーションで噴出すると同時に、職場における支配の網の目を突き破る職場反戦の運動としても体現されていた。
この時期(1969年8月)、反戦青年委員会では職場と街頭が対立的な運動スタイルとして語られ、職場に重点を置く主張は、中核派などから“右翼日和見主義”(ひよってる)の代名詞として批判の的になった。たしかに職場反戦の主張には、民同労働運動の統制を突破する街頭闘争への恐れから、職場重視を主張することで運動を右に持っていこうとする傾向があったことは否定できない。 右傾化する労働運動と対峙して、職場の変革と社会の変革の双方を貫く闘いを模索しようとすれば、自主管理社会主義をイメージする職場反戦や産別反戦の主張が出てくるのは当たり前である。当時、これらの主張は高見圭司さん、樋口篤三さん、寺岡衛さん、石黒忠さん、小野寺忠明さんらが中心となった雑誌『根拠地』が体現しており、後に主体と変革派を名乗る社青同構造改革派も、『根拠地』を支える一員であった。ところが『根拠地』的な存在は、その後の反戦青年委員会運動の中で多数派を占めることがなかった。反戦青年委員会に結集する多くの青年労働者は軍団としての党派反戦の側に獲得されたのである。68年に垣間見られた社会革命的な運動の要素があっけなく消え失せ、カリカチュア的なレーニン主義に基づく党派軍団化の道に圧倒的多数の反戦青年委員会運動がなぜ進んでいったのか。その原因は、日本の政治・経済・社会構造の何に由来するのか。反戦青年委員会を取り上げたこの論考で考えたかったのは、この点の総括の進化なのである。
全国反戦の解体
全国反戦の解体も、実はこの点と深く絡み合っている。全国反戦世話人であった今野さんが、その解体を71年6月と明言したのは理由がある。71年6月、全国反戦主催の沖縄闘争の集会が明治公園で行われたが、その場で中核派、解放派の反戦部隊が激突したのである。反戦青年委員会の主軸をなした両党派の軍団化した部隊による内ゲバ的激突によって、総評の鬼っ子といわれた反戦青年委員会は、名実ともに終わりを遂げた。
反戦青年委員会運動はその後、社会党・総評ブロックの内部にいた左翼活動家と新左翼系労働運動活動家が合流して始まった全労活運動に引き継がれていった(全労活が主催する第1回全労交集会1972年)。
一方、70年代前半に入ると総評労働運動は、公労協の戦闘化と地域労働運動の活性化で最後の輝きを示すが、その頂点であるスト権スト(1975年)の敗北後、急速に衰退の道を歩み始めることとなった。そうした中で誕生したのが1977年に発刊された「労働情報」である。
「労働情報」は反戦青年委員会・全労活と続いた新左翼労働運動の流れを継承すると同時に、1975年春闘での日経連のガイドラインを突破し、“西高東低”と言われた全金大阪地本、とくに全金田中機械支部を中心とする港合同の運動と結合して誕生した。その意味で「労働情報」は、反戦青年委員会運動の総括を生かしつつ、衰退を開始しつつあった総評労働運動と内在的にかかわり、総評内部の左派と新左翼との結合によって、総評に替わる左翼労働運動の形成を目指そうとしたのである。
総評の解散と連合結成
だが「労働情報」のこのような試みは、81年に顕在化した労働戦線の“右翼的”再編によって、大きな試練に直面することとなった。“右翼的”再編がなぜ、日本の労働運動の圧倒的多数を獲得して総評の解散と連合結成にまで至ったのか。それは、その政治的、経済的、社会的根拠を明らかにできないまま、単線的な“左翼結集”の対応で終始したからである。
今後の運動の展望とかかわるこれらの総括は、極めて重要である。
このような状況をもたらした背景には、世界と日本を貫く政治、経済、社会の大きな変容が存在しており、それに対応できなかった新・旧左翼の限界が厳然として存在している。そのことに関して、厳しく問い返さなければならない。とくに今日、金融恐慌を契機に新しい運動の可能性が噴出しつつある事態を見るならば、この負の遺産を次世代に受け継がせないためにも、それを直視し総括することが改めて問われているように思われる。

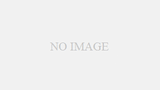

コメント